
倉庫を使用しなくなったときの処分方法に悩む人もいると思います。自力での倉庫の解体も可能なものの、経験のない場合は、業者に依頼したほうが良いでしょう。この記事では、倉庫解体の費用相場や安くするコツ、注意点を解説します。
倉庫の解体費用の相場

倉庫の解体費用は、建物の構造により大きく異なります。ここでは、木造と鉄骨造の費用相場を解説します。
木造の場合
木造の場合、費用相場は15,000〜25,000円/坪が目安です。頑丈な造りの鉄骨造よりも、比較的簡単に解体できるため、費用は抑えられます。
鉄骨造の場合
鉄骨造の場合、費用相場の目安は20,000〜30,000円/坪です。解体によって発生する廃材が多くなるため、手間が増え、その分処分費用も上がります。
解体費用に影響する要因

建物の大きさや状態、土台の有無など費用に影響を及ぼす要因がいくつか存在します。ここからは、解体費用に影響する要因を解説します。
建物の大きさによる影響
建物の大きさを把握しておくと、費用相場を算出しやすくなります。高さ・幅・奥行きから算出し、参考にすると良いでしょう。
大きさ別の費用相場の目安は、以下のとおりです。
- 10坪未満:45,000~50,000円/坪
- 10~20坪:30,000円/坪
- 20~40坪:25,000~30,000円/坪
- 50~70坪:30,000~55,000円/坪
- 70坪以上:23,000円以上/坪
10坪未満の坪数が狭いケースは、坪単価が上がる傾向にあります。規模が広くなると、坪単価が低くても、坪数や日数が多くかかるため費用は高くなります。
状態による影響
長年雨風に当たっていると、ネジやボルトが錆び、固まっている可能性があります。建物が劣化していると、その分解体に手間がかかるため費用も上がります。
費用を正確に見積もるためにも、解体前に倉庫の劣化具合を確認しておきましょう。
土台の有無による影響
解体費用は、土台の有無でも変動します。土台は、ハンマーなど手作業で壊す作業が必要です。土台の撤去には手間がかかるため、費用が高くなります。
特に木造倉庫やプレハブは、コンクリートの土台が設けられている場合が多く、費用が高くなる傾向があります。
残存物の有無による影響
倉庫内に機器や設備、備品が残っている場合は、それらの撤去費用も発生します。解体前に自己処理できる物品は、できるだけ廃棄するか売却するなどして、処分しておくと良いでしょう。
設置場所による影響
建物前の道路幅や、近隣建物との距離も費用に影響する要因です。設置場所によって、重機を入れるかどうかが決まってきます。重機が入れないような場所は、手作業が増えるため日数や人件費がかかり解体費用が高くなります。
養生による影響
倉庫解体するとき、騒音や振動、ほこりを防止するために養生を設置するのが一般的です。養生は、解体工事で発生する粉じんの発散、騒音や振動による被害を最小限に留めてくれます。
建材の細かい破片や、ほこりが周囲に飛散すると、近隣の住民の所有物を汚してしまう可能性があります。工事中のトラブル防止のためにも、養生費用を考慮しておきましょう。
解体費用を安くする方法

倉庫を解体するのであれば、費用はできるだけ抑えたいものです。ここからは、解体費用を安くする方法を紹介します。
自分で解体する
倉庫の規模によっては、自分で解体することも可能です。解体の手順は、屋根から内装、壁、床と「上から下へ」の順番で進めます。
自分で解体する場合の注意点は、以下のとおりです。
作業に必要な道具を準備する
ハンマー、バール、レンチ、チェーンソー、はつり機などを準備しましょう。
作業に必要な服装を準備する
作業着、安全靴、ヘルメット、防塵マスク、保護眼鏡、軍手などを準備しましょう。
道路使用許可の申請をする
工事車両を一般道に停車させる場合、警察署に道路使用許可の申請をしなければいけません。
建設リサイクル法の届出をする
コンクリートやコンクリートと鉄からなる特定建設資材を使用し、かつ床面積が80m²を超える建築物の解体に必要な届出です。工事開始前7日までに届出を行いましょう。
近隣住民へ挨拶や説明をする
騒音や振動、ほこりなどが発生するケースがあるため、トラブルやクレームにならないように事前に挨拶や説明を済ませておきましょう。
害虫や害獣を駆除する
長期間放置していた倉庫の場合は、害虫や害獣が住み着いている可能性があります。いきなり解体すると、周囲にまき散らしてしまうので、発生している場合は専門業者に駆除してもらってから解体するようにしましょう。
廃棄物を適切に処理する
コンクリートブロックは、ほとんどが粗大ゴミで処分できます。しかし自治体の規定によって処理方法が異なるため、確認してから処分するようにしましょう。スチール板も粗大ゴミで処分できるものの、金属は買取業者が見つかる可能性もあるので、処分前に確認すると安心です。
解体工事後は、清掃と整地をする
廃棄物の処分やゴミの処理を行ったら、足で踏みならして平らな状態にしましょう。
建物滅失登記をする
建物を解体したあとは、1カ月以内に「建物滅失登記」の手続きをしなければいけません。手続きを依頼すると手数料が発生しますが、必要書類をそろえれば自分でもできます。
複数の業者に見積もり依頼する
解体費用を抑えるために、複数業者に見積もりを依頼しましょう。複数業者に査定してもらうことで、サービスや価格が適正なものであるか、確認できます。特に下請業者への委託をしていない解体業者は、費用が安くなる傾向にあります。
不用品は処分しておく
前述したように、残置物には処分費用が発生します。処分できるものは、あらかじめ処分しておきましょう。
売却やリサイクルを検討する
不用品の状態が比較的良い場合は、リサイクルショップで売却できる可能性があります。無料査定を活用して、相談してみると良いでしょう。仮に売却できなくても、業者によっては、無料で回収してもらえることもあります。解体の前に、不用品の売却やリサイクルを検討してみましょう。
補助金や助成金を活用する
倉庫解体は、自治体の補助金や助成金を活用できる場合があります。補助金は自治体の管轄になるので、自治体のホームページをチェックしましょう。補助金や助成金は、一定の条件があるケースがほとんどです。
まず、市区町村税をきちんと収めていることが前提となります。条件には、損壊の危険性があるほど劣化が進んでいて、周囲に悪影響を及ぼす危険性がある場合などが挙げられます。
倉庫を解体する際の注意点

事前に確認しておくべき内容を把握し、不備がないように解体しなければなりません。この項では、倉庫を解体する際の注意点を紹介します。また、解体の流れも把握しておきましょう。
倉庫解体までの流れ
- 現地調査
- 見積もり・解体業者と契約
- 工事に関する申請
- 近隣への説明、挨拶
- 解体工事の着工
- 登記手続き
事前準備を万全にする
倉庫解体を行う場合は、事前準備を万全にしましょう。
まず、建物にアスベストの有無がないか確認します。もしアスベストがあった場合は、解体計画書の作成や石綿作業主任者の選任が必要です。
また、コンクリートやコンクリートと鉄からなる特定建設資材を使用し、かつ床面積が80m²を超える建設物は、建設リサイクル法の届出をしなければなりません。工事開始前7日までに届出を行いましょう。
費用の内訳を確認する
前述の通り、複数業者の見積もりを比較して、不必要な項目がないか適正価格かを確認しましょう。費用の内訳は、以下のとおりです。
- 人件費
- 重機回送費
- 廃材処分費
- 基礎の撤去費用
- 立地条件による費用
- 養生の設置費用
- 残置物の処分費用
倉庫解体は業者に依頼しよう
倉庫解体は、専門業者に依頼するのがおすすめです。アスベストがある建物の場合は、個人で解体はできません。手続きが必要になるケースもあり、専門知識のない人が解体を行うには限界があるでしょう。解体は危険も伴う作業になるので、信頼できる業者に依頼するのが得策です。
まとめ

この記事では、倉庫解体の費用相場や安くするコツ、注意点を解説しました。倉庫の解体は、大きさや状態によって個人で行えるものの、安全面や手間を考慮すると業者に依頼するほうが安心です。複数の業者に見積もりを依頼し、納得のいく業者に解体をお願いしましょう。

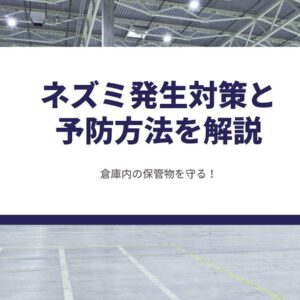 |  |

